三十三間堂とは?
三十三間堂(さんじゅうさんげんどう)は、京都市東山区三十三間堂廻町にある天台宗の寺院。建物の正式名称は蓮華王院本堂(れんげおういんほんどう)。同じ京都市東山区にある妙法院の飛地境内であり、同院が所有・管理している。元は後白河上皇が自身の離宮内に創建した仏堂。本尊は千手観音で、蓮華王院の名称は千手観音の別称「蓮華王」に由来する。
| 山号 | 妙法院に所属する仏堂につき山号はなし |
| 院号 | 蓮華王院 |
| 宗派 | 天台宗 |
| 寺格 | 妙法院飛地境内 |
| 本尊 | 千手観音 |
| 創建年 | 長寛2年(1165年) |
| 開基 | 後白河天皇 |
| 正式名 | 蓮華王院 本堂 (妙法院の一部) |
| 別称 | 三十三間堂 |
| 札所等 | 洛陽三十三所観音霊場第17番 |
| 文化財 | 本堂ほか(国宝) 築地塀、南大門ほか(重要文化財) |
拝観料
大人…600円 小人 … 300円
今年に入って4回目の参拝は、京都にある三十三間堂に行ってきました。
GWということでそこそこ人が混んでいました。
三十三間堂の由来は、南北にのびるお堂内陣の柱間が33もあるという建築的な特徴からきており、観音菩薩の変化身三十三身にもとづく数を表しています。
計1000体の観音立像は鎌倉期の再建時に、大仏師湛慶(たんけい)が、同族の弟子を率いて完成させたものです。湛慶は84歳で亡くなったそうですが、当時の鎌倉時代の平均寿命は24歳といわれており、驚異的な長寿であったことが伺えます。千手観音を完成させるという熱い使命がそうさせたのかもしれません。
観音像には、必ず会いたい人に似た像があるとも伝えられています。あいにくその姿は見つけられませんでしたが。
子どもは全く興味がないのか摺り足を使いながら、壁伝いを忍者のように移動していました。他の子も同じような動きでした(笑)
大人になったときには忘れているかもしれませんが、そういえばこの光景どこかで…くらいにでも思い出してくれたらなあと。
















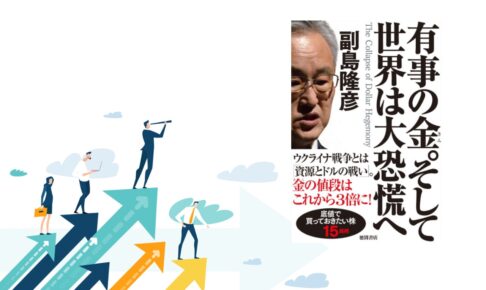



 マナブ
マナブ